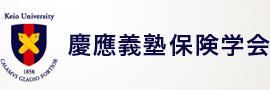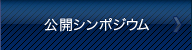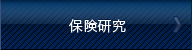大同生命保険株式会社
事業推進部 吉田 有希
本年6月からドイツのニュルンベルクに赴任し、欧州の保険業界に身を置く機会に恵まれました。「顧客保護」は、欧州でも経営理念や経営計画の中で重要な位置づけとなっており、その重みは日本と変わりません。ただし、「顧客保護」という言葉が示す意味や、その実践の仕方は日欧で違いがあるように感じます。
欧州では、消費者が一般消費財・電気・ガス等を比較考量したうえで契約できる「商品比較ポータル」と呼ばれるデジタル・プラットフォームが広く利用されています。その中には保険商品も含まれており、例えば生命保険の場合、加入目的、希望の保険金額、支払い期間などを入力すると、複数の保険会社の商品が一覧で表示され、保険料を比較することができます。
一見すると、消費者にとって非常に便利なツールのように見えます。ところが、実際には、オンラインで生保を契約する人の割合は減少傾向にあります ※1 。その理由の一つは、「わかりにくさ」にあるのではないかと思います。
商品比較ポータルで提示される保険料の中には、特定の条件を満たした場合のみキャッシュバックされるものや、複数年契約した場合の平均額が示されるものがあります。さらに、キャッシュバックの時期が不明確で、消費者自身が請求しない限り支払われないものもあります。また、問い合わせを行うと別商品の勧誘を受け、乗り換えた場合にはキャッシュバックが無効になることもあるようです。
このように、商品比較ポータルは、「少しでも安く購入できるよう比較する」という目的は果たしていても、困ったときに相談できる仕組みや顧客に寄り添ったサポートがない点は、必ずしも“顧客目線”とは言えないように感じます。しかし、欧州の消費者にとってこのプラットフォームは、自分自身で主体的に商品を選択するための大切な情報源であり、信頼できるチャネルと考えられています。実際、保険に関する情報の入手経路を確認した調査では、保険仲介人やインターネット検索を上回り、商品比較ポータルが最も多く利用されています ※2 。
これに対して日本では、顧客保護とは「顧客が迷わないよう丁寧に案内し、潜在的なニーズを引き出しながらリスクから守ること」を意味するのではないでしょうか。つまり、顧客に“寄り添い”“導く”姿勢が重視されていると感じます。
日欧の顧客保護は、どちらかが優れているというものではありません。欧州の事例は、「情報の透明性を高め、顧客自身による商品選択を支援する」という観点では、参考になるものでしょう。大切なのは、顧客保護とは単に法令を守ることではなく、消費者が納得し、安心して商品を選択できる環境を整えることだとあらためて感じました。
※1 ドイツ保険協会(GDV)の統計によると、2023年の新契約における販売経路別割合では、オンラインでの生命保険契約が2.6%となり、2020年時点の3.4%から減少
※2 一般消費者を対象とした調査(有効回答数:1,000件) 出典:pwc/Versicherungsforen